「もう食べない!」「どうせ私なんか…」 極端な言葉の奥にある 助けを求めるこころ
摂食障害の子どもと向き合っていると、
ある日突然、こう言われることがあります。
「もう食べない!」
「どうせ私なんか生きてる意味ないし…」
「全部ムリ。何もできない」「しにたい」
そんな言葉を前に、親の私たちはとても動揺しますよね。
私も何度も胸がざわつき、心が折れそうになりました。
食事のことだけではありません。
例えば…
娘が新しく買ってワンピースを試着した日。
「似合わない…私ってセンスない。もう全部ダメ」と泣き出したのです。
また別の日には、夕飯がうまく食べられなかったことで、
「もう…わからない、ムリ」と、部屋にこもってしまったことも。
私は最初、何とか励まそうとして、
「そんなことないよ」「少しずつでいいんだよ」
そう声をかけました。
でも…その言葉さえも、跳ね返されてしまうことが多かったです
■ 極端な言葉の正体は、心を守るための“防衛反応”
こうした極端な反応を目の前にすると、
「うちの子って性格的にネガティブなのかな」
「こんなに決めつけるのは、わがまま?」
そんなふうに思ってしまいそうになります。
でもある時、私は学びを通して知ったんです。
‘‘白か黒か、ゼロか100か”の考え方は、性格ではなく
「心を守るためのクセ」だということを。
人は心が追い詰められると、極端な考え方になってしまい、
「グレー」や「まあまあ」「ほどほど」といった中間地点を考える余裕がなくなります。
あいまいなものに耐えられず、
自分が傷つかないために、はっきりとした境界線を引こうとするのです
それが、「もうムリ」「全部ダメ」「しにたい」という極端な言葉になって現れます
■ “グラデーション”のまなざしで、関わっていく
このことに気づいてから、私は少しずつ関わり方を変えました。
たとえば、娘が「この服、ダメだった」と言ったとき。
「あ、この服は今日の気分じゃなかったのかも」
「今はそう思うかもしれないけど、また気持ちが変わるかもしれない」
そんなふうに、“グラデーション”のがあってもいいと捉えていきました。
白か黒かではなく「(今は)そうなんだね…」と、共感しました。
また、感情が爆発しているときには、
言葉で制するのではなく、まず「そう感じるほどつらいんだね」と、その気持ちに寄り添うこと、
感情を抑えさせるのではなく、ただそばにいるだけでいいと思う事にしました。
■ 「助けて」のサインに気づくこと
極端な言葉や態度の奥には、
実はこんな想いが隠れていることがあります。
「どうしていいか分からない」
「誰かに気づいてほしい」
「助けて」
でも子どもたちは、そのままの言葉でそれを言えないことが多い。
だからこそ、親がそのサインに気づいてあげることが大切なんだと、心から感じました。
■ あの頃の自分に、今ならこう伝えたい
あの頃の私は、
「どうしてこんなに極端なの?」と悩んでいました。
ちゃんと伝えたつもりなのに届かない…
私は何か間違っているのかな、と自分を責めたこともあります。
でも今は、こう思えるようになりました。
「極端な言葉は、その子なりのSOSなんだ」
「あなたはそれに気づこうとしていた。だから大丈夫」
■ 思考は変えられる。親子で育てていく力がある
極端な思考は、変えられます。
それには時間も、根気も必要かもしれません。
でも、「少しずつ」が必ず積み重なっていくんです。
親子で一緒に、丁寧に“グラデーションの目線”を育てていけばいい。
だから、どうか今つらい気持ちを抱えているあなたも、
自分を責めないでください。
子どもを想うあなたの気持ちは、ちゃんと伝わっています。
そして、ひとりではありません。
小さな気づきが、きっと大きな変化に繋がります。
その一歩を、一緒に歩んでいけますように。
必要な方に届きますように
⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩



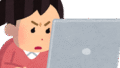
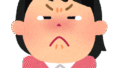
コメント